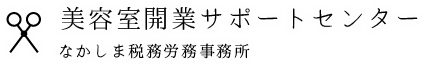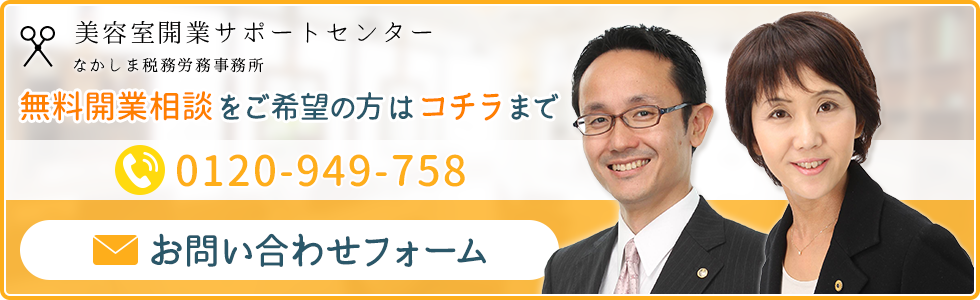給与計算における課題は?トラブルを未然に防ごう!
毎月、従業員への給料支払が発生します。
多くの企業では、経理担当者や経営者自身が、計算や管理をしていると思います。
ところで給与計算の際に関わる問題点を把握していますか?
給料のトラブルが原因で、従業員と揉めたりしたら大変です。
以下、主な課題をあげてみますので、参考にしてください。
社会保険料の控除額変更や改正に対応できていない
給与計算で一番の問題点は、社会保険・雇用保険といった社会保険の金額・税率が、現在適応するものに変更がされていない点です。
社会保険は、毎年10月支払いの給与から変更される場合が多いです。
これは、7月に標準報酬月額(保険料を決める際に基準となる月額)が見直され、それを元に控除される金額が決定されるからです。
他にも、毎月の給料が増えた・減った場合などにも標準報酬月額が変わったり、40歳になると介護保険料が加算されたりします。
また、雇用保険は、毎年4月に料率が変更となります。こういった社会保険料の変更は、見逃しやすいです。
給与計算ソフトを使っている企業だとコンピュータが自動で修正してくれますが、エクセルなどの表で管理している場合は、十分に注意しておきたいです。
従業員の扶養家族の管理ができていない
従業員の扶養家族が変化すれば、給与計算にも影響が出てくる場合が多いです。
たとえば、家族手当を導入している企業ですと、税法上の扶養家族の人数に合わせて支給されているところも多いでしょう。
扶養家族をきちんと把握しておかないと、のちに家族手当の過払いや支給不足が発覚し、従業員に請求したり、不足額を補わなければならない、といった問題点が出てきます。
従業員の家族構成について、きちんと把握しておいたほうが安心です。
また、年末調整時などに書いてもらう「扶養控除申告書」は、きちんと記載してもらいましょう。
年末調整申告時に扶養家族とした者の所得が、不要限度額を超えてしまったがために、後に不足分の税金が税務署より請求されてしまうケースも多いですから、注意したいところです。
計算間違いなどの人的ミス
給与計算が全て人的に行われていると、特に発生しやすい問題点でしょう。
単純な計算ミスから、金額の入力間違い、控除されるべきものが控除されていない、などです。
後で給与明細を確認した従業員から文句を言われ、トラブルに発展するケースも少なくありません。
人は誰でも間違いやミスを犯します。
ですから、給与担当者を二人にして二重チェックを徹底する、などの予防策をとっておくと安全でしょう。
けれども、どうしても人に任せるのは不安だ、という経営者であれば、外注に頼んでみるのも一つの手でしょう。
給与計算をアウトソーシングすれば、こうした人的ミスが減らせるのももちろん、経理担当者の負担やリスクも減らすことができますので、オススメです。